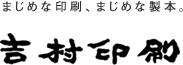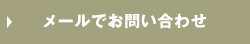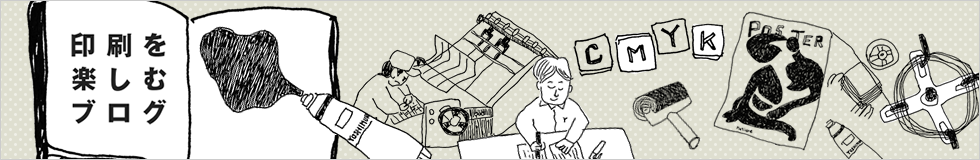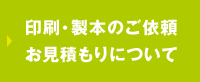最近、印刷業界界隈の話のなかで、「正直、紙の印刷物はもう厳しい」という声をよく耳にします。もう何年も前から言われていることではありますが、最近とくにいろいろな場面で「紙媒体からの脱却」という流れが強くなっているように感じています。
例えば、毎年福岡で開催されている「九州印刷情報産業展」の出店者を見ても、印刷機メーカーやCTP(印刷の版を出力する機械)メーカーの姿が年々目立たなくなり(※オフセット印刷機の展示自体がなくなり)、販売支援や経営支援、印刷業務支援のソフトやサービス関係、後加工のカッティングマシンや販促品を作製する機械の展示などが増えていて、展示の内容全体が一昔前と比べて様変わりしている印象があります。
(10年以上前の展示会は、そうはいってもオフセット機の印刷実演などがあり、とても活気があって面白かったし、印刷機メーカーのサービスの方とのお話も、入社当時はとても勉強になった記憶があります)
印刷業界全体を見てみると、出版印刷物(雑誌+書籍)の売上高が年々右肩下がりになっている一方で、全出版物に占める電子コミックの売り上げシェアは10年で6倍以上に。急伸している電子書籍市場に対して、紙の雑誌の売り上げシェアは、この10年で半減しているので、「紙媒体の出版物の減少」は“雑誌の需要の激減”が大きく響いているといっても過言ではないようです。
そんななかで、業界大手の凸版印刷が“印刷”を社名から無くして「TOPPAN」になったり、その他の中堅~大手印刷会社も“印刷”の看板を下ろしてアルファベットの社名になっていたりと、「印刷業」→「総合サービス業」のような感じになってきている流れもあります。
一方で、「“紙媒体”の印刷物がなくなっているのか」というところに関していうと、「一部の分野は減っているけど、まだまだ必要な印刷物・出版物はなくなっていない」というのが現実だと思います。
確かに売上高や印刷物全体の量自体は伸びておらず、日刊新聞も含めていろいろな紙媒体のデジタル化が進んでいる現在ではありますが、私たちは、まだまだ紙でないと表現できない、伝えられないものがあると感じています。
名刺、封筒は必需品としてまだまだ健在だし、小説や一般教養分野・教育分野などの出版物、特殊な技術を必要とする写真集や美術書、デザインやデータ処理を行なって紙媒体に表現していく技術など、多くの紙媒体がこれからの社会でもなくてはならないものです。特に小説などの単行本や文庫本をはじめとする出版物は、紙で読むからこその良さがあり、スマホやタブレットに替えられない不変の物として残っていくと思っています。
ネット印刷の台頭でチラシやポスター、パンフレットなどが手軽に印刷できるようになって便利になっている反面、「やっぱりちゃんと対面で話ができる印刷会社に頼みたい」という声もよくいただきます。
目まぐるしく変化していく時代のなかで、「温故知新」という表現が合っているかは分かりませんが、いずれまた「紙媒体の復権」があるのではないかと少し楽しみにも感じています。だからこそ、“吉村印刷にしかできない仕事”を追求して、紙の印刷にこだわり(もちろんデザイン・製本分野もこだわりながら)、お客様との対面・対話を大切に、まじめに、ときにはアグレッシブに、“かっこいい”製品づくりを追求していきたいと思っています。